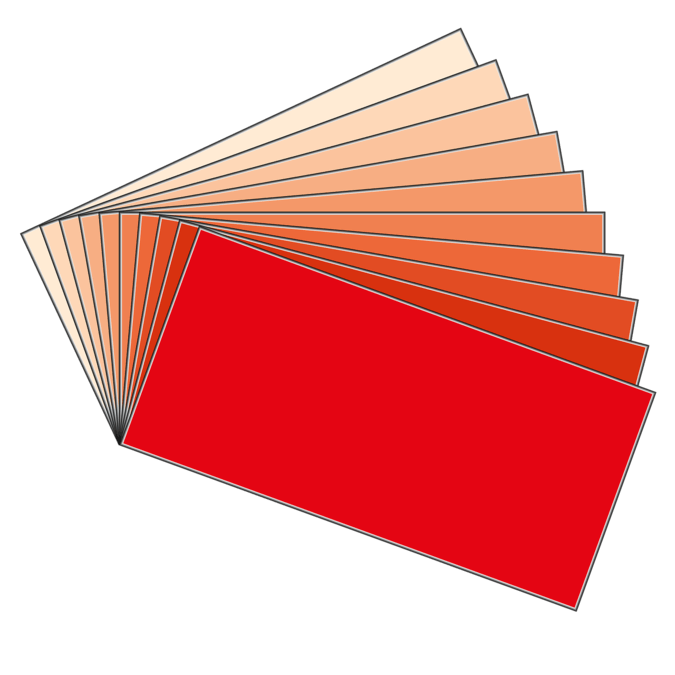見本のみで話が進んでしまう
見本工事商法を利用している業者ほど、「具体的な工事内容に触れることがない」という特徴があります。
どのような形で工事の話を進めるのかというと、手口として、「安さを追求している」ことを全面に押し出して、さらに良い物件を今まで建ててきたというふうに、ありもしない実績を持ち出すことが多いです。
今まで不動産物件に触れてこなかった人の場合、業者が人を騙すはずはないという先入観があります。
安い材料ばかりで工事を進められたとしても、安く建ててもらったのだから仕方がないと妥協することが多いのです。
ですが、本来使用する材料さえも節約して工事を進めると、生活そのものでトラブルが起きる物件の販売、もしくはサービスの契約となるため、これは見本工事商法に相当することを理解したほうが良いでしょう。
酷いケースでは、まったく行っていない工事を行ったのかのように主張し、事実がハッキリするまで自分達の非を認めないこともあります。
市場価格など曖昧な情報でごまかすことが多い
見本工事商法に引っかかってしまう人の多くは、なるべく建築にかかる費用をローコストにしたいという思いがあります。
そのため見本工事商法の事例も、以下のような市場価格について知らない人を、騙し取るようなものが多いです。
具体的には、「市場価格よりも抑えて家を建てませんか」といった対応が多く、しかも他の業者と比較して、どれほどのお金が浮くのか、そのことを事前に計算してくることが多いです。
この際にA社、B社と比較した場合というふうに、有名な業者と比較した場合もお得ですという情報を付けてきます。
これらの情報のほとんどは半分以上が嘘なので、騙されないようにしてください。
というのも手数料など、具体的な建築にかかる費用が計算されていないため、実際に家を建てる時になって、オプション料金のようなものが発生するからです。
見本工事商法は、一般の人では具体的な費用を計算できないよう、あの手この手で騙す事例が多いため、個人として建築にかかる費用を計算するのは難しいでしょう。
クーリングオフ、消費者契約法を頼りにする
一般的な見本工事商法の対処法は、民法上の詐欺であることをハッキリさせることです。
クーリングオフでお金を返すように命じる場合も、クーリングオフに応じなかった場合を想定して動いたほうが良いでしょう。
見本工事商法を利用している業者のほとんどは、明確な試算を行っていないことが多く、具体的な費用がどのような形で計算されたのか、その情報を記録していないことも多いのです。
嘘の説明でお金を騙し取る手口に一致しますので、このようなケースでは、消費者契約法4条1項1号に抵触していることを訴え、「不実告知に該当する」ことを元にして、詐欺業者を訴えるようにします。